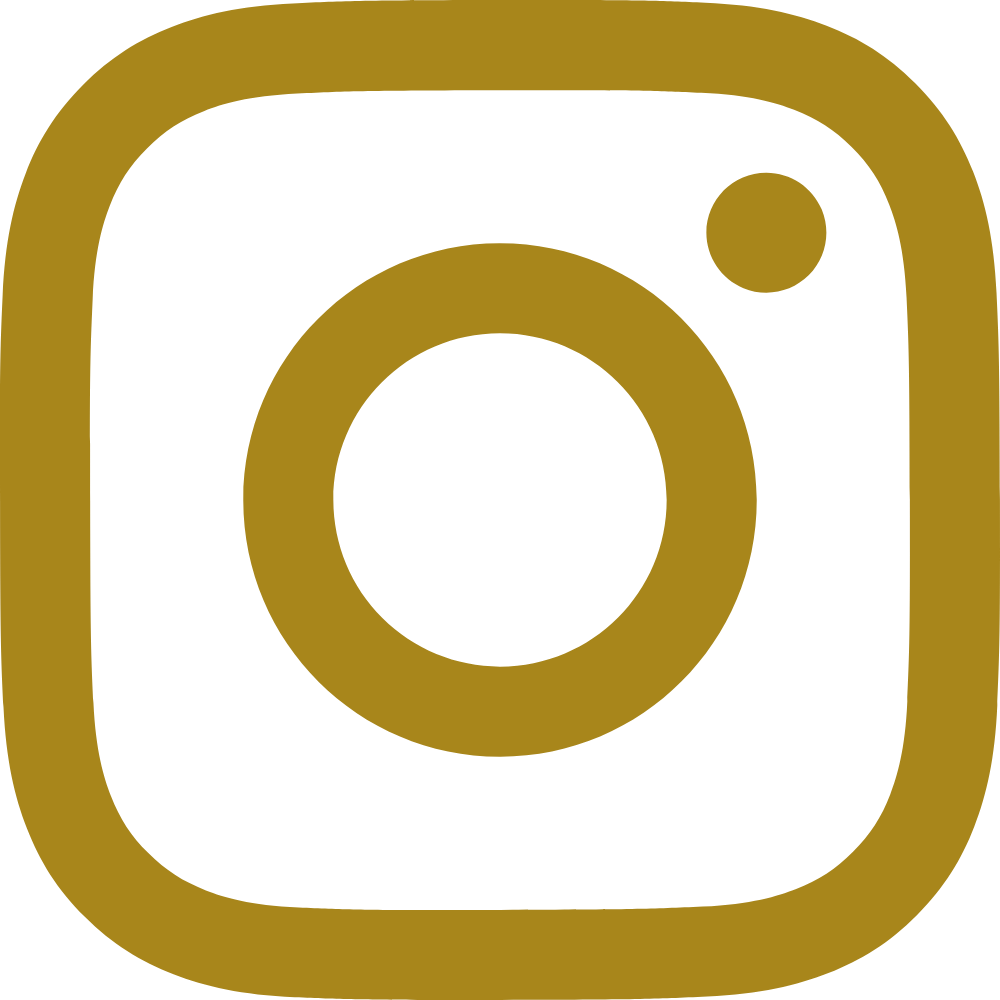先日、国際的なハイエンドイベントをモテナス日本がサポートしました!
今回の記事では、その中心となって運営に携わった、モテナス日本のコンシェルジュ2人へのインタビュー企画です。
この2人の実体験を通して、富裕層の方々を対象とした高難度なイベント運営の実態、そして“モテナス日本”というホスピタリティ・コンセプトの可能性について掘り下げていきます。
お客様のご要望とその背景
お客様からの最初のご依頼は、“ランドオペレーションをお願いしたい”っていう内容でした。具体的な内容としては、現地での導線や人の配置などの管理運営です。
実際に担当者の方と情報共有を行っていく中で、ホテルやレストランの予約をしてくださってましたが、全体設計から細部の手配も、モテナス日本で一任されました。
もともとの依頼内容から大幅に管轄する領域が広がったため、まずは関係者の方々がどこまで対応されていたのか、何を求めていらっしゃったのか、お客様の気持ちを汲み取るところから始まりました。
当日のスケジュール
体験は2日間に渡って行われました!その一部を紹介します。
- 午前中|グローバル大企業の経営者と会合
- ランチ|有名シェフによるクッキング教室
- 午後 |サムライ・相撲・ストリートカート他
- ディナー|日本食グルメによるパーティー
- アフターアワーズ |有名クラブ
印象に残っているアクティビティ・参加者の反応


2人からみて、今回のイベントを通して、特に印象に残っているアクティビティはありますか?

やはり「寿司・相撲・サムライ」の体験コンテンツですね。普通の観光体験じゃなくて、“本質的な文化を理解したい”という参加者のニーズに、しっかり応えられたと感じています。

今回の参加者の皆さんは、経営層であり、いろんな国の文化も知っていらっしゃる方々でした。だからこそ表面的なパフォーマンスでは響かないと考えました。むしろ“なぜそうするのか”という背景や技術に興味があるんじゃないかと踏んだんです。

“見せる”エンターテイメントではなく、“伝える”を大事にしたということですね。

はい。たとえばお寿司のセッションでは、ただ握るだけではなく、“この米の温度には意味がある”とか、“魚の切り方にどんな意図があるのか”まで職人の方には説明をしていただきました。そういう“職人の哲学”に触れられる時間を意識的に作りました。

職人の方にとっても、“日本人以外の方に且つ英語で、お寿司を作るそれぞれの工程に込められた意味や意図を丁寧にお伝えする”というのは初めてのことでした。それでも、”ご自身が職人として大切にされていることをお話しください”とお願いしたところ、丁寧にご準備くださりました。

お客様からは、“知識欲が満たされ、学びの多い時間だった”や“このような日本文化の真髄や裏側の部分まで見えるような見せ方をしてくださるとは思わなかった”という声を直接もらうことができ、モテナス日本として、本当に届けたい価値が、まさに形になった時間だったなと思いました。
モテナス日本だからできること

多国籍かつ多目的な大規模イベントは、想定外の事態がつきものです。計画を立てる段階では見えなかった課題が、現場に入ることで次々と浮かび上がります。
今回のイベントも例外ではなく、スケジュールのズレや参加者の急な動きなど、柔軟さが試される瞬間が何度もありました。そんな中で見えてきたのは、“全体を俯瞰しつつも、瞬時に現場を動かす対応力”が、成功の鍵になるということでした。

現場での対応は、日本語だけでは対応できない場面も多かったのでは?

そうですね。英語でのやり取りは多かったです。参加者の国籍も文化もばらばらだったので、アレルギーや宗教的な食事制限、スケジュール変更など、本当に細かい要望が常に飛んできました。

モテナス日本のスタッフは英語対応が可能ですので、通訳を介さずに直接意思疎通が図れるのは、ストレス感もなくスムーズで、また進行も止めることなくイベントの対応ができたと感じています。

モテナス日本の強みとして“現場スタッフの英語力”もあげられるわけですね。また、当日は計画通りに進まない“イレギュラー”も発生したとか…?

どのイベントにもつきものかもしれませんが、お客様が“僕はここで抜けます”や“あとから合流します”と自由参加に近い状態だったので、何人いるのかを把握するのに苦慮しました。
しかし、ちゃんと情報は共有しないと帰りのバスの時間も決められないしので、現場で連携し“情報をどうまとめて共有するか”を重要視しました。

事前に導線や人の配置をシミュレーションしていたので、こういったイレギュラーにも瞬時に対応ができたと思います。連絡を密にとり、全員がどこにいるか把握できるようにしていたのも大きかったですね。
結果的に、柔軟に動かしていったことが参加者にとっては“すべてがスムーズだった”っていう印象になったと思います。
フルオーダーメイドの伝統文化体験
今回のイベントは、既存のパッケージでは決して対応できない、まさに“フルオーダーメイド”の伝統文化体験を提供しました。
複雑な要望や突発的な変更にも即応しながら、深い文化的価値を伝える――その両立ができたのは、モテナス日本が持つ“柔軟なデザイン力”と“現場対応力”があったからこそです。
モテナス日本は、企業イベントからVIP向けの特別体験まで、お客様に合わせた“唯一無二の時間”をデザインします。
「こんなことできる?」そんな漠然としたご相談でも構いません。 ぜひ一度、私たちにお声がけください。あなたの想いを、最高の形に仕立てます。
サービスの詳細や導入の流れを知りたい方へ。
専任のコンシェルジュが丁寧にご案内しますので、お気軽にご相談ください。

30代男性ライター。ホテルに16年間勤務し、旅行業界に携わる。旅行代理店やホテルでの仕事を通じて旅行に興味を持ち、よく旅行に行っています。好きな都市は仙台と博多です。旅を通じて得た知識や日本の魅力を丁寧に伝えていきます。