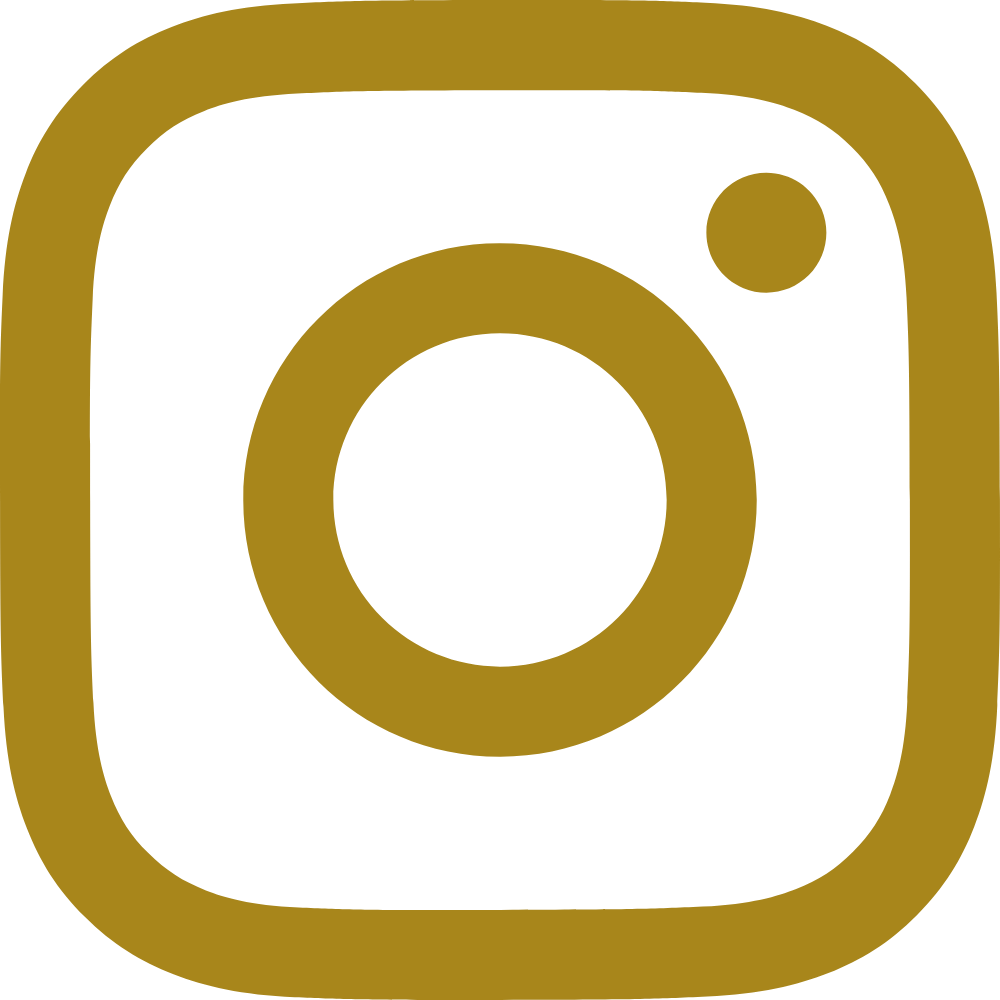日本のお祭りは、地域の伝統と神様への感謝が色濃く反映された文化行事です。
鮮やかな衣装、賑やかな太鼓の音、神輿や山車(だし)の迫力…。
多くの外国人がその非日常的な雰囲気に魅了されます。
この記事では、日本在住の方が外国人ゲストをお祭りに案内する際に役立つよう、日本の祭りの基本・特徴・季節ごとのおすすめ・英語での説明フレーズまで網羅。
おもてなしにも、日本の再発見にもなる「お祭り体験」をぜひ共有してみませんか?
日本のお祭りとは?

華やかな衣装に身を包んだ人々、響き渡る太鼓の音、町を練り歩くお神輿や山車(だし)。日本のお祭りは、目を楽しませてくれるだけでなく、その背景には神様や自然への感謝、先祖への祈り、地域の絆といった深い意味が込められています。
もともとは五穀豊穣・無病息災・災厄除けなどを願う宗教的な儀式として始まったお祭りも、時代とともに形を変え、現在では地元の人々と訪問者が一緒に楽しめる文化イベントとして親しまれています。
日本のお祭りの起源や意味を知ることで、目に映る華やかさだけでなく、その背景にある祈りや願いにも気づくことができます。まずは、お祭りがどのように生まれ、どんな想いが込められているのかを見ていきましょう。
お祭りのはじまりは「神様への感謝」
日本のお祭りの多くは、神道や仏教の行事としての起源を持っています。もともとは自然の恵みや神様への感謝を伝える「神事」として始まり、春には農作物の豊作を祈る「田植え祭」、秋には実りを祝う「収穫祭」などが全国各地で行われてきました。
例えば、京都の祇園祭は、平安時代に疫病を鎮めるために始まったもので、神の力に守ってもらうことを願った祈りの行事でした。このように、日本のお祭りは単なるイベントではなく、自然と共に生きる人々の生活そのものと深く結びついた存在だったのです。
また、神様だけでなく、先祖や土地の霊への感謝や鎮魂の意図も含まれることがあり、盆踊りなどはその代表的な例です。こうした信仰の表れが、地域の伝統として今もなお大切に守られ、現代の私たちの暮らしの中に自然に息づいているのです。
地域ごとに受け継がれる伝統行事
日本全国には、その土地ならではの個性あふれるお祭りが数多く存在します。たとえば、青森の「ねぶた祭」は、眠気を追い払うという風習が起源とされ、巨大な灯篭人形が街を練り歩く東北ならではのダイナミックなお祭りです。一方で、沖縄の「エイサー」は、祖先を迎え送り出すための踊りとして始まり、島の信仰と音楽文化が融合した独自の形をしています。
こうしたお祭りは、数百年の歴史を持つものも多く、地域の誇りや文化を象徴する存在でもあります。衣装、掛け声、踊り、神輿や山車の装飾に至るまで、代々地元の人々によって受け継がれ、守られてきた伝統がそこにはあります。
また、お祭りの準備には多くの住民が関わり、世代を超えて協力するため、地域社会の絆を深める重要な役割も担っています。まさに、日本のお祭りは「見るもの」であると同時に、「支えるもの」「参加するもの」でもあるのです。
時代とともに変化する“祈り”のかたち
日本のお祭りは、時代の流れとともに少しずつその姿を変えてきました。かつては主に宗教的な意味合いの強い行事として、神社や寺の境内を中心に執り行われていましたが、現代では観光イベントや地域振興としての側面も強くなっています。
たとえば、かつて地域の限られた人々だけが関わっていたお祭りが、いまでは全国・海外からの観光客も巻き込んでオープンな体験型イベントとして開催されるようになりました。屋台やパレード、音楽イベントなども加わり、子どもから大人まで誰もが楽しめるエンターテインメント性の高いお祭りも増えています。
それでも、お祭りの本質が失われたわけではありません。神様や自然、祖先への感謝と祈りという根本的な精神は、今もなおお祭りの中心に据えられています。変わりゆく社会の中で、伝統と現代が共存するかたちで進化しているのが、日本のお祭りの魅力とも言えるでしょう。
このように、時代に合わせて柔軟に形を変えながらも、心をつなぐ文化として生き続けているのが、日本のお祭りのすごさなのです。
また、祈りの心は形を変えても、日本の精神文化に息づいています。その静かなかたちのひとつが、禅の世界です。

日本のお祭りを説明する英語フレーズ
| 日本語の意味 | 英語フレーズ |
|---|---|
| 「お祭り」は日本の伝統文化のひとつです。 | “A matsuri is one of Japan’s traditional cultural events.” |
| 神様や自然に感謝するために行われます。 | “It’s held to give thanks to the gods and nature.” |
| 季節や地域によって内容が変わります。 | “Each region and season has its own unique festival style.” |
| お祭りでは伝統的な衣装を着たり、太鼓をたたいたりします。 | “People wear traditional clothes and play drums during the festival.” |
| 古代日本では、五穀豊穣や厄よけ祈願などの祈りを込めて人々の暮らしに寄り添っていました。 | “In ancient Japan, it was a part of people’s daily lives with prayers for a good harvest and protection from bad luck.” |
日本のお祭りの特徴|お神輿・だんじり・盆踊りとは?
威勢のいい掛け声とともに町を練り歩くお神輿、絢爛豪華な山車、スピード感あふれるだんじり、みんなで踊る盆踊り、夜空を彩る花火大会。日本のお祭りは、地域ごとに異なる「らしさ」や「伝統」が息づいた、五感で楽しめる文化体験です。
目の前の迫力や華やかさに圧倒されるだけでなく、その一つひとつに歴史的な背景や人々の想い、地域の誇りが込められています。お祭りの要素を少しだけ深掘りすることで、訪れる側も迎える側も、より豊かな体験につながるはずです。
お神輿(みこし)|神様が宿る“移動式の神殿”

お神輿とは、神様が一時的に宿る「乗り物」です。お祭りの期間中、地域の氏神様を神社からお神輿に移し、人々の手によって街中を練り歩きます。これは、神様に町を巡ってもらい、災いを祓い、福をもたらしてもらうという意味があります。
神輿を担ぐ際には「わっしょい!」「せいやっ!」といった勇ましい掛け声とともに、何百人もの担ぎ手が力を合わせて進みます。ときには大きく揺さぶったり、上に持ち上げたりと、神様に喜んでもらうための“動き”も見どころです。
地域によって神輿のデザインや担ぎ方には違いがあり、東京の三社祭や神田祭、大阪の天神祭などは特に有名です。その迫力と一体感に、外国人ゲストも圧倒されることでしょう。
太鼓台・山車(だし)|動く芸術作品とお祭りの誇り

山車(だし)とは、お祭りで引かれる豪華に装飾された大型の台車で、神輿と同様に神聖な存在とされることもあります。太鼓や笛の音とともに町を練り歩くその姿は、まさに“動く芸術品”。金箔や彫刻で美しく飾られた山車は、地域の技術と誇りの結晶です。
「太鼓台」と呼ばれるタイプは、特に関西地方や四国地方に多く見られ、巨大な太鼓を中心に据え、力強いリズムと掛け声でお祭りを盛り上げます。
たとえば、秩父夜祭(埼玉)や博多祇園山笠(福岡)などでは、山車が夜の街をライトアップしながら進む様子がとても幻想的。装飾の美しさとスケールの大きさに、初めて見る人は誰もが感動します。
祭車・だんじり|スピードと熱気の極致!

「だんじり」は、主に関西地方に見られるスピード感と迫力が魅力の“曳き山車(ひきだし)”です。
中でも有名なのが「岸和田だんじり祭(大阪)」で、高さ4メートルを超える巨大なだんじりを、全力疾走で街中を曳き回す様子は圧巻。曲がり角を勢いよく回る「やりまわし」という技は、このお祭りのハイライト。数十人の曳き手が息を合わせ、観客の歓声とともに突き進む様子は、まるで命をかけたパフォーマンスのようです。
木彫りの装飾や提灯の灯りなど、夜の演出も見どころのひとつ。勇壮さと美しさが共存するお祭りとして、国内外の多くの観光客を魅了しています。
盆踊り|踊ってつながる夏の風物詩

「盆踊り」は、お盆の時期に行われる伝統的な踊りで、先祖の霊を迎え、感謝の気持ちを伝える行事として始まりました。円を描くように踊ることで、人と人、そして過去と現在がつながるとされており、日本独特の精神文化を象徴しています。
踊りのスタイルは地域によってさまざまで、阿波踊り(徳島)や郡上踊り(岐阜)などのように、観客も一緒に踊れるお祭りも多く存在します。浴衣を着て踊る姿、太鼓と笛の音、夜空に浮かぶ提灯の光…。そんな風景は、日本の夏を彩るやさしくも懐かしい風物詩です。
外国人ゲストにとっても、気軽に参加できるお祭り体験として非常に人気が高く、国籍を超えて一体感を味わえる貴重な機会となります。

花火|夜空を彩る“祈り”と祝福の光

花火は日本の夏祭りに欠かせない存在ですが、もともとは神様への祈りや悪霊払いの意味を持っていたとも言われています。その歴史は江戸時代までさかのぼり、隅田川花火大会をはじめ、全国各地で行われる大規模な花火大会は今や夏の風物詩。
夜空に大輪の光が咲き誇るその瞬間、観客からは思わず歓声が上がります。特に、音楽と連動した打ち上げや水上花火など、日本ならではの演出は外国人にも強い印象を残します。
浴衣を着て、屋台グルメを楽しみながら花火を眺める。そんな時間は、日本の「非日常」を体験できる最高のおもてなしのひとつです。

日本のお祭りの特徴を説明する英語フレーズ
| 日本語の意味 | 英語フレーズ |
|---|---|
| 花火大会も日本の夏祭りの楽しみのひとつです。 | “Fireworks are a highlight of summer festivals in Japan.” |
| 観光客でも盆踊りに参加できますよ。 | “Even visitors can join Bon Odori, the traditional festival dance.” |
| 神輿が町を巡るのは、神様に地域を見てもらい、守ってもらうという信仰的意味合いがあります。 | “The mikoshi is carried through the town so that the deity can see the community and bless it with protection. This reflects a traditional belief that the gods watch over the area during the festival.” |
| 地域の人たちが、歴史や文化とつながる大切な行事なんです。 | “They are a way for local people to connect with their community and history.” |
外国人に人気の日本のお祭り8選|季節ごとにご紹介

日本には一年を通して、季節ごとに多彩なお祭りが各地で開催されています。春は花の開花や子どもの日のお祭りとともに華やかに始まり、夏は夜空に咲く花火と踊りの輪が広がり、熱気あふれるお祭りが各地を盛り上げ、秋は紅葉とともに勇壮な山車やだんじりが街を駆け抜け、冬は白銀の雪に包まれ、幻想的な風景の中で静かに行われます。自然とともに暮らしてきた日本人の感性が、季節ごとのお祭りのかたちに表れています。
訪れるタイミングによって出合えるお祭りが変わるのも、日本旅行の大きな楽しみのひとつ!外国人ゲストにとっても、その時期ならではの「日本らしさ」を感じられる絶好のチャンスです。
春・夏・秋・冬、それぞれの季節におすすめの代表的なお祭りをピックアップしてご紹介します。
※2025年8月現在の情報、開催期間は公式サイトでご確認ください。
春のお祭り
春は新しい季節のはじまり。桜の開花や暖かな気候とともに、各地で華やかなお祭りが開催されます。自然の美しさと伝統が重なる、春ならではのお祭りを楽しんでみましょう。

浅草三社祭(東京)|東京随一の迫力を誇る神輿祭り
毎年5月の第3週末に開催される「三社祭」は、東京都浅草・浅草神社で行われる江戸っ子の熱気と伝統が詰まったお祭りです。このお祭りの最大の見どころは、3基の本社神輿と約100基もの町会神輿が街を練り歩く壮観な光景。神輿を担ぐ法被姿の担ぎ手たちが、力強く「わっしょい!」と声を上げながら進む様子は、まさに“日本のエネルギー”そのものです。
神輿が町を巡るのは、神様に地域を見てもらい、守ってもらうという信仰的意味合いがあり、観光イベントでありながらも地元の誇りと信仰が色濃く残る行事として、今も真剣に受け継がれています。
お祭りの期間中、浅草寺周辺には多数の屋台が立ち並び、たこ焼きや焼きそば、かき氷など、日本の“縁日グルメ”も楽しめるのも魅力のひとつ。また、雷門や仲見世通りなど浅草の観光名所との距離が近いため、観光とお祭り体験を一緒に味わえるスポットとして、外国人旅行者にも非常に人気です。
| 浅草三社祭 ※今年(2025年)は開催終了 | |
|---|---|
| 開催日(2025年) | 5月16日(金)~18日(日) |
| 時間帯 | 初日:13:00~、2日目:12:00~、最終日:08:00~ |
| 会場 | 浅草神社・浅草寺周辺(東京都台東区) |
| アクセス | 東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草駅」すぐ |
| 公式サイト | 三社祭 公式サイト |
弘前さくらまつり(青森)|日本の“桜の名所”で味わう春の絶景
「弘前さくらまつり」は、毎年4月中旬から5月初旬にかけて開催される、桜とお城とお祭りが融合した春の風物詩です。会場となる弘前公園は、弘前城跡を中心に広がる広大な敷地に約2,600本の桜が咲き誇る、日本でも有数の“桜の名所”として知られています。
このお祭りの特徴は、桜そのものの美しさに加えて、花見文化とお祭りの要素がバランスよく組み合わされていること。
日中は堀沿いの桜並木や「花筏(はないかだ)」と呼ばれる水面に浮かぶ花びらが絶景をつくり、夜はライトアップされた夜桜が幻想的な雰囲気を演出します。
園内には多数の露店が並び、津軽の郷土料理やご当地グルメを味わいながら、花見客が思い思いの時間を過ごしています。
また、ボートでお堀を巡る体験や、着物レンタルでの散策、和太鼓などのステージイベントも用意されており、視覚・味覚・体験すべてで「日本の春」を満喫できるイベントです。
海外メディアにもたびたび紹介されるこのお祭りは、“一度は訪れたい日本の春”を代表する旅先として、外国人観光客からの注目度も年々高まっています。
| 弘前さくらまつり ※今年(2025年)は開催終了 | |
|---|---|
| 開催日(2025年) | 4月16日(水)~5月5日(月・祝) |
| 時間帯 | 屋台:9:00~21:00 ライトアップ:日没~22:00(延長日は夜23:00まで) |
| 会場 | 弘前公園(青森県弘前市) |
| アクセス | JR弘前駅より「道テマチループバス」乗車、市役所前下車 |
| 公式サイト | 弘前さくらまつり公式サイト |
夏のお祭り
太鼓の音が響き、浴衣姿の人々が集う夏祭り。花火や盆踊りなど、にぎやかで熱気あふれるイベントが日本の夏を彩ります。
思わず心が躍る、夏ならではのお祭りを体感してみましょう。
祇園祭(京都)|日本三大祭のひとつ、1000年続く“動く美術館”
祇園祭は、毎年7月1日から31日まで1ヶ月にわたって開催される、日本を代表する歴史的なお祭りのひとつです。京都・八坂神社の祭礼として、平安時代から約1000年以上続く伝統を持ち、日本三大祭の一つにも数えられています。
最大の見どころは、7月17日の「前祭(さきまつり)」と24日の「後祭(あとまつり)」に行われる山鉾巡行(やまほこじゅんこう)です。高さ25m、重さ12トンにも及ぶ絢爛豪華な山鉾が、祇園囃子の音色に包まれながらゆっくりと市内を巡る姿はまさに壮観で、「動く美術館」とも称されます。
山鉾には西陣織やペルシャ絨毯など世界各地の美術品が用いられ、その装飾の美しさも国際的に高く評価されています。
期間中は町中がお祭り一色となり、提灯の灯りがともる宵山(よいやま)や、限定グッズや浴衣姿の観客でにぎわう夜の屋台も大きな楽しみ。京都の町並みと調和した「静かな熱気」と格式高い伝統が融合する祇園祭は、日本文化の奥深さを体感できる夏のハイライトです。
| 祇園祭 ※今年(2025年)は開催終了 | |
|---|---|
| 開催日(2025年) | 7月1日~31日 |
| 時間帯 | 山鉾巡行:前祭7月17日、後祭7月24日 |
| 会場 | 八坂神社~京都市内各所 |
| アクセス | 市バス「祇園」下車すぐ |
| 公式サイト | 祇園祭公式サイト |
青森ねぶた祭|武者絵の山車と跳人(はねと)が街を熱くする
東北地方最大級の夏祭りとして知られる「青森ねぶた祭」は、毎年8月2日〜7日にかけて開催されます。お祭りの主役は、高さ5m、幅9mを超える巨大な「ねぶた」と呼ばれる山車(だし)たち。武将や神話をモチーフにした勇壮なねぶたが、光を灯しながら夜の街を練り歩く様子は、まるで歴史絵巻が動き出したかのようです。
ねぶたの周囲では、「ラッセラー!ラッセラー!」の掛け声とともに、“跳人(はねと)”と呼ばれる踊り手たちが跳ね続け、観客のボルテージも最高潮に。しかも、事前に衣装をレンタルすれば誰でも跳人として飛び入り参加可能というのも、このお祭りの魅力のひとつです。
最終日には、ねぶたが海上を流れる「海上運行」と花火大会が同時に行われ、光・音・人の熱気がひとつになった圧巻のフィナーレを迎えます。
迫力、美しさ、参加型の楽しさをすべて備えた青森ねぶた祭は、“日本の夏の情熱”を体感できる代表的イベントとして、外国人からの人気も非常に高く、リピーターが多いのも納得の魅力です。
| 青森ねぶた祭り ※今年(2025年)は開催終了 | |
|---|---|
| 開催日 | 8月2日~7日(毎年) |
| 時間帯 | 2〜6日:18:45または19:00~21:30 7日:13:00〜15:30 |
| 会場 | 青森市中心部 |
| アクセス | JR青森駅から徒歩約10分 |
| 公式サイト | 青森ねぶた祭り公式サイト |
秋のお祭り
実りの秋は、感謝と祝福の季節。紅葉が彩る中、勇壮なだんじりや華やかな奉納踊りが街を盛り上げます。地域の伝統と人々の誇りが息づく、力強い秋のお祭りを味わってみましょう。
岸和田だんじり祭(大阪)|命がけの“やりまわし”が観客を沸かせる、迫力の祭礼
大阪府岸和田市で毎年9月に開催される「岸和田だんじり祭」は、スピードと勇壮さが魅力の日本屈指の動的なお祭りです。このお祭りで使用される「だんじり」とは、総重量4トンを超える木製の山車(やま)。その上には彫刻や提灯で飾り付けがされ、屋根の上には踊り手が立ち、お祭りをさらに盛り上げます。
最大の見どころは「やりまわし」と呼ばれる、狭い街角を全速力で方向転換する技。数十人の曳き手たちが全力疾走でだんじりを引き、カーブを一気に曲がる様子は、観客も思わず息を呑むほどの迫力です。このお祭りは、ただのイベントではなく、町ごとに誇りをかけて参加する「地域総出の勝負」。参加者たちの表情や掛け声からも、だんじりに対する強い情熱と伝統への誇りが伝わってきます。
お祭り前には安全祈願や神事も行われ、信仰と娯楽が見事に融合した地域文化の象徴として、国内外から多くの人が訪れます。
| 岸和田だんじり祭 | |
|---|---|
| 開催日(2025年) | 9月7日、12日〜14日 10月5日、11日、12日 ※日程は毎年異なる |
| 時間帯 | 朝〜夜間にかけて断続的に開催 |
| 会場 | 岸和田市内各地区 |
| アクセス | JR東岸和田駅すぐ |
| 公式サイト | 岸和田市公式サイト |
長崎くんち(長崎)|異文化が融合した絢爛豪華な秋の踊り祭り
「長崎くんち」は、毎年10月7日〜9日に長崎市の諏訪神社で開催される、約400年の歴史を持つ秋の大祭です。このお祭りの魅力は、長崎が古くから海外と交流のある港町だったことから生まれた、日本と異文化が融合した独特の演出にあります。
一番の見どころは、「奉納踊(ほうのうおどり)」と呼ばれる出し物の数々。中国の龍舞、オランダ風の傘踊り、豪華な船の山車「御座船(ござぶね)」などが、ダイナミックな動きとともに披露される様子は、他のお祭りにはない魅力です。
演技は市内の7つの踊町(おどりちょう)が年ごとに担当し、地域住民が長期間にわたって準備し、練習を重ねて完成させる渾身のパフォーマンス。また、演目ごとに舞台装置のような山車が登場し、観る者を圧倒します。
華やかさ・音楽・異文化の香りが交差する長崎くんちは、外国人観光客にとっても親しみやすく、心躍る秋祭りです。
夜の街に響く太鼓と笛の音が、長崎の秋を華やかに彩ります。
| 長崎くんち | |
|---|---|
| 開催日 | 10月7日~9日(毎年) |
| 時間帯 | 日中~夜 |
| 会場 | 諏訪神社周辺・長崎市中心 |
| アクセス | 長崎駅から路面電車で数分 |
| 公式サイト | 長崎くんち公式サイト |
冬のお祭り
寒さが深まる冬、日本各地では雪や火を使った幻想的なお祭りが開催されます。静寂の中に輝く光や、厳かな神事が心に響くこの季節。冬だからこそ味わえる、日本ならではの美しいお祭りをご紹介します。
札幌雪まつり(北海道)|雪と氷がつくり出す壮大なアートの世界
「札幌雪まつり」は、毎年2月に北海道・札幌市で開催される、日本を代表する冬の観光イベントです。会場となる大通公園には、全長20メートルを超える雪像や、繊細な氷像が立ち並び、街全体がまるで“雪の美術館”のような雰囲気に包まれます。
雪像はアニメキャラクターや歴史的建造物など、毎年テーマが変わるため何度訪れても楽しめるのが魅力。夜になるとライトアップが施され、幻想的でフォトジェニックな風景が広がります。
また、スケートリンクやチューブスライダーなどのアクティビティも充実しており、子ども連れの観光客にも大人気。寒さを忘れるほどに盛り上がるこのお祭りは、「日本の冬」を体感できる代表的な体験として、海外からのリピーターも多く訪れています。
| さっぽろ雪まつり | |
|---|---|
| 開催日(2026年) | 2月4日~11日 |
| 時間帯 | 10:00~21:00(最終入場20:30) |
| 会場 | 大通公園ほか(札幌市) |
| アクセス | 地下鉄「大通駅」「すすきの駅」などすぐ |
| 公式サイト | さっぽろ雪まつり |
なまはげ柴灯(せど)まつり(秋田)|恐怖と神聖が入り混じる“雪と火”の神事
秋田県男鹿市で2月に行われる「なまはげ柴灯(せど)まつり」は、雪山の中で鬼のような姿をした“なまはげ”が登場する、東北の神秘的な冬祭りです。
“なまはげ”とは、藁(わら)でできた衣装と鬼の面を身につけた神の使いで、怠け者や悪い子を戒める存在として地元で信仰されています。このお祭りでは、神社の神聖な火を囲みながら、なまはげたちが雪の山道を下りてくるという、神事としての厳かさと圧倒的な迫力が同居する幻想的な光景が広がります。
会場ではなまはげ太鼓の演奏や、民俗舞踊、地元の郷土料理なども体験でき、観光客でも“東北の神話世界”に触れられる貴重な機会です。夜の雪景色と松明の炎、そしてなまはげの叫び声が響く空間は、ただ観るだけではない、“感じるお祭り”として記憶に残ること間違いなしです。
| なまはげ柴灯(せど)まつり | |
|---|---|
| 開催日 | 毎年2月の第2土曜日を含む金・土・日 |
| 時間帯 | 夜間開催(例:18:00~20:30) |
| 会場 | 真山神社(秋田県男鹿市) |
| アクセス | 男鹿駅から臨時バスで約30分 |
| 公式サイト | なまはげ柴灯まつり公式サイト |
春夏秋冬のお祭りを伝える英語フレーズ

| 日本語の意味 | 英語フレーズ |
|---|---|
| 日本では四季折々の美しさを映した、色とりどりで個性豊かなお祭りが一年を通して行われています。 | In Japan, colorful and unique festivals take place throughout the year, each reflecting the beauty of the changing seasons. |
| 日本三大祭りとは京都の祇園祭、大阪の天神祭、東京の神田祭りです。 | “The three major festivals in Japan are Kyoto’s Gion Festival, Osaka’s Tenjin Festival, and Tokyo’s Kanda Festival.” |
| 祇園祭は平安時代から1000年以上続いていて、もともとは疫病退散を祈る行事だったんです。 | “The Gion Festival has been held for over 1,000 years, originally to pray for protection from epidemics.” |
| 散った花びらが水面を覆う様子を「花筏」と呼びます。とても風情がある春の景色です。 | “When fallen petals cover the water’s surface, it’s called “hanaikada,” or “flower raft.” It’s a poetic spring scene in Japan.” |
| 「ねぶた祭り」の山車(だし)は武将や神話をモチーフにした勇壮なねぶたが、光を灯しながら夜の街を練り歩き、まるで動く歴史絵巻のようです。 | “At the Nebuta Festival, giant illuminated floats featuring heroic warriors and mythological figures parade through the night streets. It’s like watching a living picture scroll from Japanese history.” |
お祭りをもっと特別に!モテナス日本の旅プラン

モテナス日本では、お祭りのワクワク感と文化の魅力をたっぷり味わえる特別ツアーをご用意しています。現地ならではの特別なスポットや、頼れるガイド、面倒な手配も全部おまかせ。観光だけじゃ物足りない!という方にぴったりです。
旅の計画から当日のサポートまでしっかりカバーするので、あとは日本の四季のお祭りを思いきり楽しむだけ。祇園祭の迫力、満開の桜の美しさ、東京の夏の夜のにぎわいまで、どの瞬間も本物の魅力と心地よさでいっぱいです。
祇園祭を裏側まで満喫できるプレミアム京都体験

京都で開催される日本を代表するお祭り「祇園祭」を、特別な視点から楽しめるプレミアム体験です。山鉾巡行は、英語対応ガイドの案内で特等席から観覧。普段は入れない山鉾の作業場を見学したり、宵山の夜には、用意された浴衣で提灯が灯る風情ある街並みを散策します。
さらに、町家での茶道体験や山鉾曳きへの参加など、ここでしかできない体験も満載。専用送迎やプロカメラマンによる写真撮影も含まれ、祇園祭をスタイリッシュかつ深く味わえる特別なプランです。
秘密の桜スポットと文化体験|春限定の特別リトリート

まるで平安の貴族になったような気分で、春の桜を堪能する贅沢な旅を体験できます。花びらが舞う露天風呂付きの絶景旅館に連泊し、朝は湯けむりとともに桜の香りに包まれて目覚めます。日中は文化ガイドが案内する知る人ぞ知る桜の名所を巡り、人混みとは無縁の静けさの中で写真撮影や散策を満喫。
体験メニューも盛りだくさん。やわらかな桜色の生地で包む桜餅作り体験、そして本格的な茶室での着物姿の茶会は、この旅ならではの特別なひととき。
夜は三味線の生演奏を聴きながら日本酒を味わい、提灯に照らされた幻想的な小径をそぞろ歩き。伝統・美・癒しがひとつに溶け合う、心に残る“春の日本”を全身で感じる旅です。
浴衣で楽しむ!東京の夏祭りと花火クルーズ

東京の夏祭りを、ワンランク上の特別なスタイルで楽しむキュレーション体験。
まずはプロによる浴衣の着付けで、夏祭り気分を高めます。その後は、ディナー付き屋形船から眺める隅田川花火大会で、夜空を彩る花火を間近に。さらに、みたま祭では優先入場と舞台裏見学がついており、一般では見られない貴重な光景を体験できます。
地元ガイドの案内で盆踊りに参加し、地元の人々と交流。移動は冷たいドリンクやおしぼりが用意された快適な専用車でラクラク。フィナーレは、東京の夜景が一望できるルーフトップビアガーデンで乾杯し、夏の余韻を味わいます。
華やかさ、快適さ、そして日本の夏文化の魅力が詰まった、一生の思い出になる祭り旅です。
訪日外国人におすすめ!日本のお祭りで最高の“おもてなし”体験!

日本のお祭りには、華やかな演出や迫力ある神輿・山車、心をひとつにする踊りや太鼓の響き、そして人々の祈りや感謝の気持ちが込められています。地域ごとの個性と伝統が光るその場には、言葉の壁を越えて感動できる“体験”がたくさん詰まっています。
外国人ゲストにとって、日本のお祭りはただの観光イベントではなく、文化を体で感じられる貴重な時間となります。そして私たち日本人にとっても、お祭りは改めて自分たちの文化の奥深さに触れ、誰かと分かち合いたくなる“誇り”の瞬間です。
年に一度の特別なひとときこそ、最高のおもてなし。ぜひ大切なゲストと一緒に、日本のお祭りの魅力を味わってみてください。
-1-300x200.png)

旅をこよなく愛するWebライター。アジアを中心に16の国にお邪魔しました(今後も更新予定)。
ワーホリを機にニュージーランドに数年滞在。帰国後は日本の魅力にとりつかれ、各地のホテルで勤務。
日本滞在が、より豊かで思い出深いものになるように、旅好きならではの視点で心を込めてお届けします!