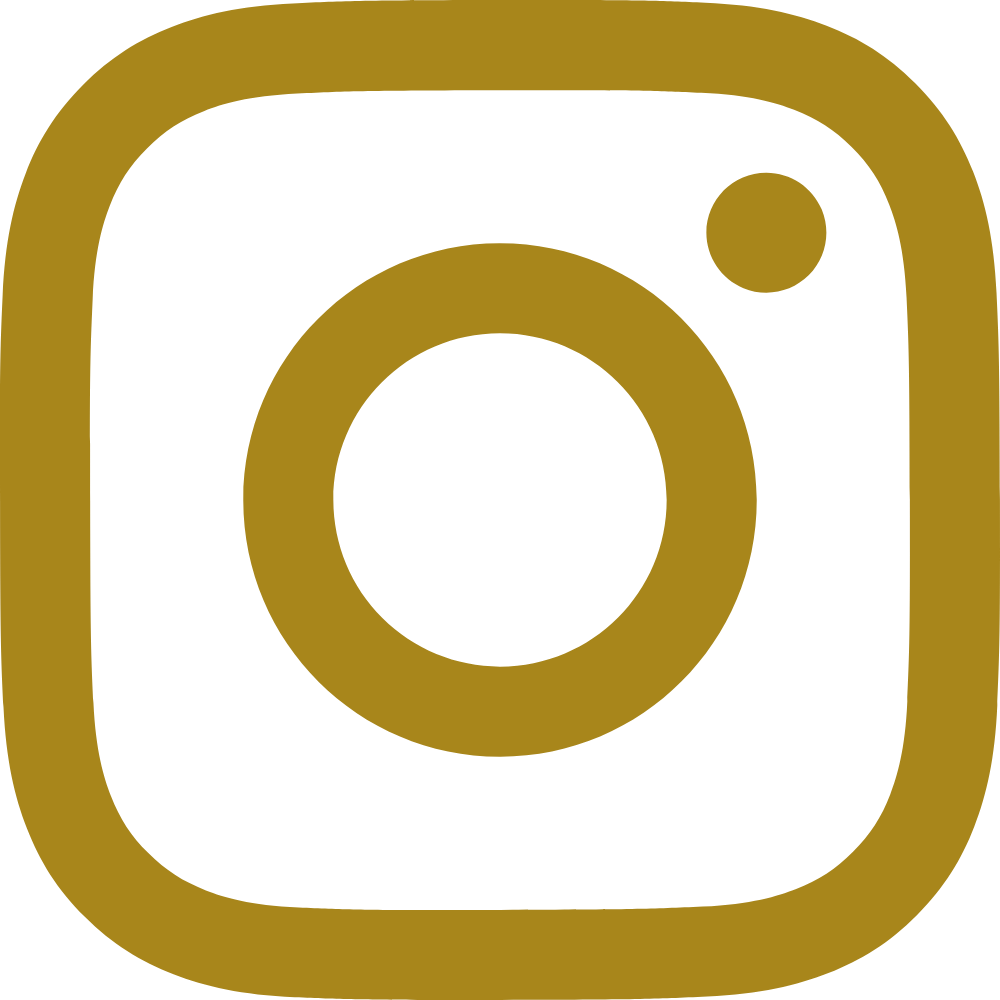夏、日本各地で行われる「お盆」は、ご先祖さまの霊を迎えて敬う、日本独自のあたたかな伝統行事です。
実はこの文化、アジアのさまざまな国でも似た風習が根付いており、共通する“いのちへの思い”が感じられます。外国人観光客の間でも、お盆は「見て美しく、体験して心に残る」行事として人気が高まっています。
日本のお盆の由来や各地の風習、海外との共通点、そして外国人との文化交流につながる体験型イベントなど、お盆をさまざまな視点からひもときながら、日本文化の深さと温かさに触れていきましょう。
日本のお盆とは

お盆は、日本で昔から行われている、亡くなったご先祖さまを思い出し、感謝の気持ちを伝える行事です。仏教の考えと、日本の伝統的な信仰が合わさって生まれました。多くの人が家族で帰省してお墓参りをし、ご先祖さまを家に迎えて、数日間いっしょに過ごすという思いが込められています。地方によって少しずつやり方は違いますが、大切にしている心は同じです。
お盆の起源と歴史
お盆の始まりは、仏教のお経「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」に出てくるお話がもとになっています。これはインドで始まり、中国を経て日本に伝わったものです。
目連(もくれん)というお坊さんが、苦しんでいる亡き母を助けたいと願い、たくさんの僧侶に食べ物をお供えしたことで母が救われた、という内容です。この考えが日本に伝わり、昔からあったご先祖さまを大切にする信仰と結びつき、奈良時代には貴族の間で、江戸時代には庶民の間にも広まっていきました。
今では宗教行事というよりも、家族で集まってご先祖さまを大切にする、身近な行事になっています。
お盆の期間と地域差
多くの地域では、毎年8月13日から16日がお盆の時期です。この時期はちょうど夏休みや会社の休みと重なることが多く、実家に帰る人が増えるので、新幹線や高速道路がすごく混むことでも知られています。
東京など一部の地域では、「新盆」といい7月にお盆をするところもあります。これは昔、カレンダーが新しくなったときに、日付のずれが生まれたことが理由です。さらに沖縄や奄美の地域では、旧暦でお盆を行う「旧盆(きゅうぼん)」が今でも続いています。
時期は違っても、どの地域でもご先祖さまへの思いは変わりません。
お盆に行われる代表的な風習
お盆の時期になると、家の前などで「迎え火(むかえび)」や「送り火(おくりび)」を焚く家庭が多く見られます。これは、ご先祖さまが迷わず家に来て、安心して戻れるようにとの願いを込めた火です。
また、「盆踊り」は昔、亡くなった人の魂をなぐさめるために始まった踊りで、今では地域のお祭りとして子どもから大人まで楽しめる行事になっています。さらに、キュウリやナスで作る「精霊馬(しょうりょううま)」や、供物(くもつ)と呼ばれる食べ物や花をお供えする風習もあり、家族みんなで先祖を思う時間として大切にされています。
京都の「大文字送り火」や徳島の「阿波踊り」などは、にぎやかに行われる伝統イベントのひとつです。とても有名で、多くの観光客が訪れるイベントとなっています。
海外にもお盆はある?

日本のお盆と同じように、ご先祖さまを思い出して供養する文化は、実は世界のいろんな国にもあります。
アジアを中心に、宗教や風習に合わせてそれぞれの形に進化していて、「日本と似てるな」と思う点もあれば、「こんな考え方もあるんだ」と驚く違いも。国ごとの行事を比べてみると、日本文化のことも、ちょっと違った角度から見えてくるかもしれません。
海外お盆文化の一覧比較
| 国・地域 | 行事名 | 時期 | 特徴 | 共通点(日本との) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 中元節 | 旧暦7月15日 | 地獄の門が開いて霊を供養する | 祖先供養・食物供え |
| 台湾 | 中元節(鬼月) | 旧暦7月 | 供養屋台が街中に出る | 死者の霊を慰める |
| ベトナム | Vu Lan(ヴーラン) | 旧暦7月15日 | 母親への感謝が中心 | 仏教的・祖先敬意 |
| タイ | Sart Thai (サトー・タイ) | 旧暦10月15日ごろ(9〜10月) | 寺院で供物を捧げて先祖や無縁仏を供養 | 功徳を通じて先祖を思う仏教文化 |
| 韓国 | 秋夕(チュソク) | 旧暦8月15日 | 墓参りや伝統料理 | 家族帰省・墓参共通 |
| メキシコ | Día de Muertos (死者の日) | 11月1〜2日 | カラフルな祭壇とガイコツ装飾 | 死者との再会文化 |
中国・台湾:中元節と鬼月の霊供養文化

中国の「中元節」は、仏教の盂蘭盆と道教の三官信仰が結びついてできた行事で、旧暦7月15日に霊を供養する日とされています。霊界の扉が開かれ、この世に戻ってくる霊をもてなすと考えられており、灯籠流しや紙銭を燃やすなど、死者のためのさまざまな儀式が行われます。
台湾ではこの一か月を「鬼月」と呼び、死者の霊が自由に動き回るとされ、地域や企業単位での大規模な供養行事が行われるなど、社会的にも広く根づいた文化になっています。
ご先祖さまを大切に思う気持ちが生活の中に自然と溶け込んでいます。
ベトナム:Vu Lan(ヴーラン)と家族への感謝

ベトナムの「Vu Lan(ヴーラン)」は、仏教的な先祖供養の行事であると同時に、「親孝行の日」としての意味も持っています。
仏教では目連尊者が母を救った伝説にちなんで、母親に感謝を伝える日とされ、赤や白のバラを胸に飾る風習があります。多くの人がこの日に寺を訪れ、感謝の念を込めた読経や供養を行う姿は、日本のお盆の静かな祈りと共鳴します。
また、短期間の出家をして徳を積むことで、先祖や親への恩を返そうとする人も多く、精神的な深さが感じられます。
タイ:Sart Thai(サトー・タイ)と先祖供養の儀式

「Sart Thai(サトー・タイ)」は、タイで旧暦10月15日前後に行われる仏教の行事で、先祖供養の日として広く知られています。
この日、人々はお寺に足を運び、亡くなった家族や親族の霊に食べ物やお供えを捧げ、徳(功徳)を積むことで来世の幸福を願います。地域によっては、無縁仏への供養も行われます。特に南タイを中心に根付く伝統行事です。
儀式は日本のお盆とは異なりますが、「故人を思い、供養する」という心は共通しており、アジア各地に根付く死者への敬意を感じられる行事です。
韓国:秋夕(チュソク)と家族再会

韓国の「秋夕(チュソク)」は、旧暦8月15日の満月の日に祝われる伝統的な祭日で、収穫を祝う意味と先祖への感謝を込めた儀式が行われます。
多くの家庭では、先祖の墓を清掃して礼を捧げ、その後、家族が集まって「ソンピョン(松餅)」などの伝統料理を囲みます。この時期には交通渋滞が発生するほど人々が故郷へ帰るため、日本の帰省ラッシュと非常によく似ています。
伝統衣装の韓服を着て行う礼拝など、文化的アイデンティティの再確認の場にもなっています。
メキシコ:Día de Muertos(死者の日)のカラフルな供養文化

メキシコの「Día de Muertos(死者の日)」は、死を悲しむのではなく、「死者との再会を喜ぶ日」として祝われます。
家庭では「オフレンダ」と呼ばれるカラフルな祭壇が作られ、先祖の写真や好物、花(特にマリーゴールド)で飾られます。お墓でピクニックをする家族や、ガイコツの仮装を楽しむ子どもたちの姿が印象的で、死を明るく受け入れる価値観が感じられます。
静かに祈る日本のお盆とは対照的ですが、「先祖とのつながりを思い出す時間」である点は深く共通しています。

世界各地の先祖供養文化を見比べることで、「亡くなった人を大切に思う気持ち」は宗教や国境を超えて広く共有されていることがわかります。それぞれの形に、その土地の考え方や暮らしぶりが色濃く反映されているのが興味深いところです。
お盆体験が外国人に人気な理由

お盆の行事は、日本の文化や価値観を深く体現したものとして、外国人からも高い注目を集めています。中でも、体験を通じて得られる“感情の共有”や“精神的な癒し”は、他の観光アクティビティとは一線を画す魅力といえるでしょう。
静かな祈りの時間や、地域とのふれあい、そして命を思う文化的背景。それらが織りなす体験は、訪れる人の心に深く残ります。
視覚的な美しさ:送り火や灯籠流し
夜の暗闇にふわりと浮かぶ送り火の灯りは、ただ美しいだけではありません。亡き人を見送るという意味を知った上でその光景を目にすると、多くの外国人が言葉を失い、静かな感動を覚えます。
火と水という自然の要素が融合した灯籠流しでは、無数の灯りが川を流れる様子に“魂の旅立ち”を重ね、深いスピリチュアル体験として心に残ると語られることが多いです。
暗い夜に浮かぶやさしい灯りは、幻想的でどこか神秘的な雰囲気を漂わせ、京都の「五山の送り火」や長崎の「精霊流し」などはその代表例です。こうした行事は、フォトジェニックでSNS映えすることもあり、写真や動画を通じて海外でも広まりやすく、日本文化のイメージとして強く記憶されるきっかけにもなっています。
盆踊りのリズムと一体感
盆踊りは、日本人にとって夏の風物詩であり、地域の絆を象徴する行事でもあります。
また、誰でも参加できる開かれたお祭りとして外国人にとっても、踊りの輪に加わることで“言葉のいらない交流”を体感できる貴重な機会となります。太鼓の音に合わせて手足を動かすうちに、場の一体感に自然と溶け込むことができ、参加者同士に笑顔と連帯感が生まれます。
「観光客」としてではなく、「一人の参加者」として歓迎される経験は、観る文化から“共に踊る文化”への入り口として、多くの人が日本への親しみを深めています。
日本独自の“命”の哲学
お盆の根底には「命は一人のものではない」という考え方が息づいています。亡くなった人と、今を生きる私たちが心の中でつながり続けるという思想は、合理性を重んじる現代の価値観とは対照的な“静かな豊かさ”を感じさせます。
日本人が自然や祖先を敬い、日々の暮らしに感謝する姿勢は、多くの外国人にとって新鮮で感動的に映ります。実際に「お盆を体験して心が落ち着いた」「日本人の静かな祈りに感動した」と語る外国人も増えています。
形式やルールの奥にある“心の在り方”が、お盆の最大の魅力なのです。
おすすめの「お盆体験×日本文化」企画

お盆は見るだけの行事ではなく、感じて、体験してこそ心に残る文化です。特に外国人の方々にとっては、参加型の体験を通じて、日本の精神性や人とのつながりを実感することができます。
静かな送り火に心を癒され、盆踊りで地域の人々と笑顔を交わし、手を動かして精霊馬を作ることで日本文化の細やかさに触れる。
そんな体験は、日本旅行の特別な思い出になるはずです。
モテナス日本では、そんな“感じるお盆”をテーマに、伝統文化と結びついた特別な体験プランを用意しました。
夏の日本ならではの風景と空気の中で、地域の人々と交流しながら行事の意味を知り、五感で楽しむ。ただの観光では得られない、深い満足感がそこにあります。
ここでは、外国の方にも安心して参加いただける、わかりやすく親しみやすい体験型プログラムを4つご紹介します。
※クリックすると企画の詳細に移動できます


① 祈りの灯りを見送る「送り火×灯篭流し体験」

静かに流れる川面に、自分の手で作った灯篭を浮かべる。そんな体験は、日本の「祈りの文化」に直接触れる貴重なひとときです。灯篭に込めるのは、亡き人への想いや、今ある日々への感謝の言葉。灯りが水面をゆらめきながら遠ざかっていく光景は、言葉を超えて心に響きます。
地元の方々と一緒に準備や儀式を体験することで、行事の意味や地域ごとの思いも自然に共有され、忘れられない文化交流となるでしょう。
② 日本の夏を感じる「浴衣×盆踊り体験」

夏の夜に浴衣をまとい、地元の人たちと輪になって踊る。この体験は、視覚、聴覚、体の動きすべてを使って、日本の季節感や地域の絆を肌で感じられるひとときです。
モテナス日本が提供する体験には、着付けワークショップや伝統舞踊のミニ講座も含まれ、踊りの背景や意味を知ったうえで参加できます。踊りの後は、屋台の味を楽しんだり、記念写真を撮ったりと、まるで地域の一員になったかのような没入感を味わえるでしょう。
-1-300x200.png)

③ ご先祖を想う手仕事「精霊馬&供物づくり体験」

「キュウリの馬、ナスの牛」として知られる精霊馬は、ご先祖さまがこの世を行き来する乗り物とされ、お盆の象徴的な存在です。
モテナス日本が提供するワークショップでは、単に工作を楽しむだけでなく、供物に込められた意味や精霊信仰の背景を学ぶ時間も設けられています。お子さま連れの家族にも好評で、世代を超えて日本文化を共有できる貴重な機会となります。
地元の野菜を使うなど、地域性を活かした演出も可能です。
④ 和の心にふれる「墓参り×茶道体験ツアー」

モテナス日本が提案するこのプログラムでは、寺院での墓参りを文化解説付きで体験したあと、茶室へと場所を移し、茶道の静かな所作と心を味わいます。墓参りの意義や日本人の死生観について、住職やナビゲーターから丁寧な説明があるため、単なる参拝ではなく“学びの時間”として印象に残ります。
茶道体験では、和菓子の意味や季節の器づかいなど、目に見える所作を通して「もてなしの心」に触れることができます。精神性と美意識が交差する、日本らしい深い時間が流れます。


お盆にまつわるよくある質問(FAQ)
お盆って仏教のイベント?それとも日本独自のもの?
お盆はもともと仏教に由来する行事ですが、今では宗教を超えた日本の文化行事として多くの人に親しまれています。家族や地域のつながりを大切にする習慣として、信仰に関係なく広がっています。
海外でも“お盆みたいな行事”ってあるの?観光客も参加できる?
はい、あります!台湾の「鬼月」やメキシコの「死者の日」など、誰でも楽しめる開かれた先祖供養のイベントが各国にあります。写真を撮ったり一緒に体験したりできるものも多く、観光客にとっても魅力的です。
旅行中でも楽しめる?日本のお盆イベントおすすめは?
「京都の大文字送り火」や「徳島の阿波踊り」、「長崎の精霊流し」などは、観光客にも大人気の行事です。浴衣をレンタルして盆踊りに参加する外国人も多く、地域のお祭りに自然と溶け込めるチャンスです。
お盆とハロウィンって似てる?どう違う?
どちらも「死者が帰ってくる」というテーマはありますが、雰囲気はまったく違います。お盆は静かでスピリチュアルな時間、ハロウィンは楽しくにぎやかな仮装イベント。死に対する文化の違いが見えてくる比較です。
外国人にお盆を説明するなら、どう伝えたらいい?
「Japanese All Souls Festival」「spiritual homecoming for ancestors」などの英語表現が分かりやすいです。家族の絆や亡き人を思い出す行事と伝えることで、多くの人が興味を持ち、共感してくれるでしょう。写真や実際の体験談を添えると効果的です。
お盆文化を通して、世界と心をつなぐ

お盆は、日本の大切な供養文化でありながら、アジア各国にも通じる共通の精神が息づいています。見て楽しむだけでなく、実際に体験することで、その奥にある「いのちを思いやる心」に触れられるのが、この行事の本当の魅力です。
外国人にお盆を伝えることは、日本文化を紹介するだけでなく、人と人とのつながりや感謝の気持ちを共有するきっかけにもなります。ぜひ、あなた自身も「迎える側」として、お盆の心を世界に伝えてみてはいかがでしょうか。
モテナス日本では、「お盆」と「日本文化」を組み合わせた企画の提案が可能です。
通訳の手配、会場のご相談なども承ります。他ではできない「お盆×日本文化体験」をしたい方、外国人のお客様をおもてなししたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

旅をこよなく愛するWebライター。アジアを中心に16の国にお邪魔しました(今後も更新予定)。
ワーホリを機にニュージーランドに数年滞在。帰国後は日本の魅力にとりつかれ、各地のホテルで勤務。
日本滞在が、より豊かで思い出深いものになるように、旅好きならではの視点で心を込めてお届けします!